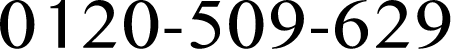会社設立
(商業登記)
平成18年5月1日に会社法が施行されました。
会社を設立される方にとって一番大きな利点は、会社法の施行によって、設立時の出資額規制が撤廃されたこと、取締役1名で設立できること、役員の任期を10年まで伸長できることです。
この出資額規制の撤廃によって資本金1円で会社が設立できることになりました。
実際に1円で会社を設立すると、すぐに債務超過となってしまいますのである程度の資本金は必要ですが、資本金が1,000万円必要であったことを考えると、株式会社の設立は格段にしやすくなりました。
会社は、作ることより、その後どのように経営していくかが重要です。
会社設立の段階から、将来どのように経営していくかを見据えることがとでも大切になってきます。
当事務所では、設立時の機関設計、資本金、役員の任期等のコンサルティングを行い、また設立後の役員の任期管理、登記相談もアフターサービスとして行っています。
また、会社を設立後、法務・税務等様々な問題が発生した場合、税理士、弁護士、社会保険労務士等の専門家のご紹介することも可能です。
※電子定款認証に対応済みのため、印紙代40,000円がかかりません。
会社を設立するメリット・デメリット
メリット
- 所得を分散できるため節税効果がある
- 社会的信用が高い
- 資金調達がしやすい
- 退職金により節税することができる
- 株式会社は有限責任である
デメリット
- 税務申告の複雑化
- 均等割りによる法人住民税7万円(赤字でも支払義務あり)
- 交際費に限度額がある
- 社会保険への加入が強制
- 会社設立登記費用、役員変更登記費用等の各種登記費用がかかる